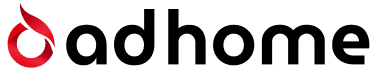海と山に囲まれ、美しい街並みが広がる神戸市。 その一方で、海からの湿気を含んだ風や、冬場の六甲おろしによる急な気温の変化は、「夏のジメジメ」や「冬の結露」といった、住まいの悩みの原因にもなりがちです。
「エアコンをつけても、なんだか空気がスッキリしない…」 「毎朝、窓の結露を拭くのが大変。カビが生えないか心配…」
そんなお悩みの解決の鍵を握るのが、実は、部屋の大部分を占める**「壁」**の存在です。 今回は、私たち株式会社アドホームが、毎日深呼吸したくなるような、心地よい空気環境をつくるための「壁材選び」について、プロの視点から詳しく解説します。
Part 1: なぜ今、湿気をコントロールする「調湿する壁」が注目されるのか?
近年の住宅は、断熱性・気密性が非常に高くなりました。これにより、外の暑さや寒さの影響を受けにくく、快適な室温を保ちやすくなった一方、室内の湿気が外に逃げにくいという側面もあります。
湿気がこもると、カビやダニの発生、アレルギーの原因になるだけでなく、家の柱や土台を傷めることにも繋がりかねません。
そこで重要になるのが、①計画的な換気 と ②壁自身の調湿機能 の二段構えです。 24時間換気システムで空気を入れ替えつつ、壁材が室内の湿度に応じて湿気を吸ったり吐いたりしてくれれば、まるで家そのものが呼吸しているかのように、一年を通して快適な湿度を保ちやすくなるのです。
Part 2: 代表的な「調湿建材」の種類と、アドホームが大切にする視点
調湿機能を持つ壁材には様々な種類があります。ここでは代表的な3つの素材について、それぞれの特徴と、私たちが施工する上で大切にしているポイントをご紹介します。
1. 珪藻土(けいそうど)
植物性プランクトンの化石からできる自然素材。無数の微細な孔(あな)が、高い調湿性能を発揮します。
メリット: 調湿性能が非常に高い。消臭効果や耐火性も。
デメリット: 表面が少し粉っぽく、手でこすると落ちやすい場合がある。
アドホームの視点: 珪藻土の性能は、塗り方や厚み、下地の処理で大きく変わります。私たちは、左官職人の確かな技術で、見た目の美しさはもちろん、素材の持つ力を最大限に引き出す丁寧な施工を心がけています。
2. 漆喰(しっくい)
サンゴ礁がルーツの消石灰を主成分とする、古くから日本の城郭やお寺にも使われてきた伝統的な素材です。
メリット: 調湿性に加え、アルカリ性のためカビにくく、抗菌作用も期待できる。年月とともに硬くなり、耐久性が増す。
デメリット: 施工に時間と手間がかかる。乾燥時に細かなひび割れ(ヘアークラック)が入ることも。
アドホームの視点: 漆喰の白く滑らかな質感は、空間に品と落ち着きを与えてくれます。私たちは、この日本の気候風土に合った素晴らしい素材の魅力を、現代の住まいに活かすご提案をしています。
3. 機能性壁紙(ビニールクロス)
ビニールクロスに調湿や消臭などの機能を付加したものです。
メリット: コストを抑えやすく、デザインや色のバリエーションが豊富。お手入れも簡単。
デメリット: 珪藻土や漆喰ほどの高い調湿効果は期待できない場合が多い。
アドホームの視点: ご予算やお手入れの手軽さも大切な要素です。例えば、「家族が長く過ごすLDKや寝室は漆喰にして、汚れやすい子供部屋や廊下は機能性クロスにする」など、適材適所の考え方でお客様に最適なプランをご提案します。
Part 3: 後悔しない壁材選びのためのQ&A
Q. 自然素材は高いイメージが…。全部に使わないと意味ないですか?
A. いいえ、そんなことはありません。Part2でも触れたように、LDKや寝室など、過ごす時間が長く、快適性を特に高めたい空間に限定して採用するだけでも、空気感の違いを十分に実感いただけます。ご予算に応じたメリハリのある使い方をご提案しますので、ご安心ください。
Q. 実際の質感や色を、見て確かめることはできますか?
A. もちろんです。壁材は、カタログや小さなサンプルで見るのと、広い面積で見るのとでは印象が大きく変わります。アドホームでは、様々な素材のサンプルをご用意しているほか、完成見学会などで実際の空間を体感いただく機会も設けています。ぜひ、ご自身の目で、手で、その質感を確かめてみてください。
まとめ:壁材選びは、心地よい暮らしをデザインすること
壁は、単なる間仕切りや飾りではありません。 家の性能を支え、空気環境を整え、日々の暮らしの心地よさをデザインする、とても重要な要素です。
私たち株式会社アドホームは、ご紹介したような様々な素材の特性を熟知した上で、神戸の気候風土と、何よりお客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添い、「我が家の空気が一番好き」と思っていただけるような家づくりを目指しています。
素材選びで迷ったら、ぜひお気軽にご相談ください。一緒に、深呼吸したくなる家を考えましょう。